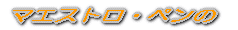 
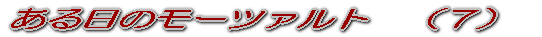
4月20日
1786年4月20日、モーツアルトは名作オペラ「フィガロの結婚」を完成させます。ヴィーンに居を構えて4年、モーツアルトは30歳になりました。「フィガロ」が初演されたのはそれから十日後の5月1日。上演後モーツアルトは作曲料として450フローリンを、台本作者のロレンツォ・ダ・ポンテは200フローリンを受け取っています。現在の貨幣価値に直すとどれくらいなんでしょう。いずれにせよモーツアルトは厚遇されてますね。
それにしても毎度驚くのは書き上げてから初演までの短さですよ。オペラはどんな順序で作曲するのでしょうね。この時代のオペラはナンバーオペラと言って、レチタティーヴォ(語り部分)を間に挟んで、1番、2番という風に番号が付いた音楽が並んでいます。様々な手紙の記述から類推すると、彼はまずレチタティーヴォから作曲を進めています。そして各幕のフィナーレや合唱の入るナンバーを書き、各歌手のアリアやデュエット等は、その歌手本人に会ってから書きますから、後回しですね。ですから他の都市からの注文ですと、その地へ行ってから書く訳で、当然上演ぎりぎりに仕上がるのでしょう。もちろんできた順に写譜屋に回され歌い手に届きますから、全曲を十日で練習した訳ではありませんが、なんともせわしない話です。
私達がオペラをやる時は、歌の稽古もさる事ながら、演技の追求にしつこい程の時間をかけますよ。ドラマの精神に則って、各配役の心の動きや感情の表現を深く深く読み下げて行きます。それが動きの裏付けになり、ひいては歌の表現へと結びついて行きます。わずか十日やそこらでそんなレベルまで行けるとはまさか思えませんね。当時のオペラは音楽に焦点が当てられ、演技は二の次だったのでしょうかね。一説によると、それ以前のオペラではアリアを歌う定位置てのがあったと言いますから、ドラマと関係無く動いてその場所へと行った訳で、やはり演技はそれ程重要ではなかったのかな。
しかし各役柄の内面を想像して、演技の裏付けを探る作業は面白いですよ。この「フィガロ」では、スザンナと伯爵夫人が入れ替わって伯爵を騙す場面がありますが、それを知らないフィガロは・・・さぞ辛かったろうなあ。ところでこのオペラではフィガロは一度も散髪の仕事しないなあ。なんでかなあ。
 
|

