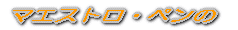 
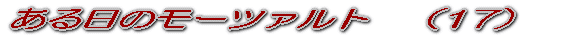
2月12日
1785年2月12日、モーツアルトは自宅にヨーゼフ・ハイドンを招き、K.458,464,465の3曲の弦楽四重奏曲(いわゆるハイドン・カルテットの後半3曲)を演奏しました。ハイドンは同席していた父レオポルトに対し次のような賛辞を述べています。
「私は誠実な人間として神かけて申し上げますが、御子息は私が個人的に知っている、あるいは名前だけ知っている全ての作曲家の中で最高の方です。」
モーツアルトが初めてのクラヴィア曲を書いたのは5歳の時、最初の交響曲は8歳、最初のオペラは11歳。なのに最初のカルテットは14歳の時です。ちょっと遅い気がしますね。それも最初のイタリア旅行中、悪天候で足止めを喰ったため「退屈しのぎに」書いたものだそうな。やれやれ、退屈しのぎに名作を書かれたのでは、世の凡庸な作曲家達はたまりませんよ。
この時書いた最初のカルテット(K.80「ローディ」)を除いて、モーツアルトのカルテットには全てハイドンの影がつきまといます。「ミラノ・カルテット」「ヴィーン・カルテット」「ハイドン・カルテット」のいずれもがハイドンの作品の影響下に書かれています。つまりハイドンの音楽に触発されて作曲した訳ですね。現在では滅多に取り上げられないハイドンですが(2009年の没後200年なんて、何の騒ぎも無く過ぎちゃいました)、当時は周囲に最大の影響を及ぼした最高の作曲家だったのです。
しかし「ハイドン・カルテット」は前作より10年近い中断の後に書かれた労作です。さすがのモーツアルトをしても前作を凌ぐような深い精神性を音楽に込めるのは簡単ではなかったらしく、彼自身もこの作品は苦労の末に生まれた、と述べています。あのモーツアルトも何でもスラスラと苦労も無く出来た訳ではないんですね。ふふふ、それを知るとますますヴォルフガングの事が好きになります。
天才とはきっと、努力する事を忘れない人の事を言うんですね。同時に出来た物が価値ある美しさを持っているか判断できる、高度な審美眼も必要です。ふう、やっぱり作曲家にならなくてよかったなあ・・・・。
  |

